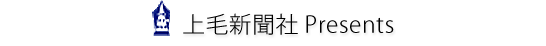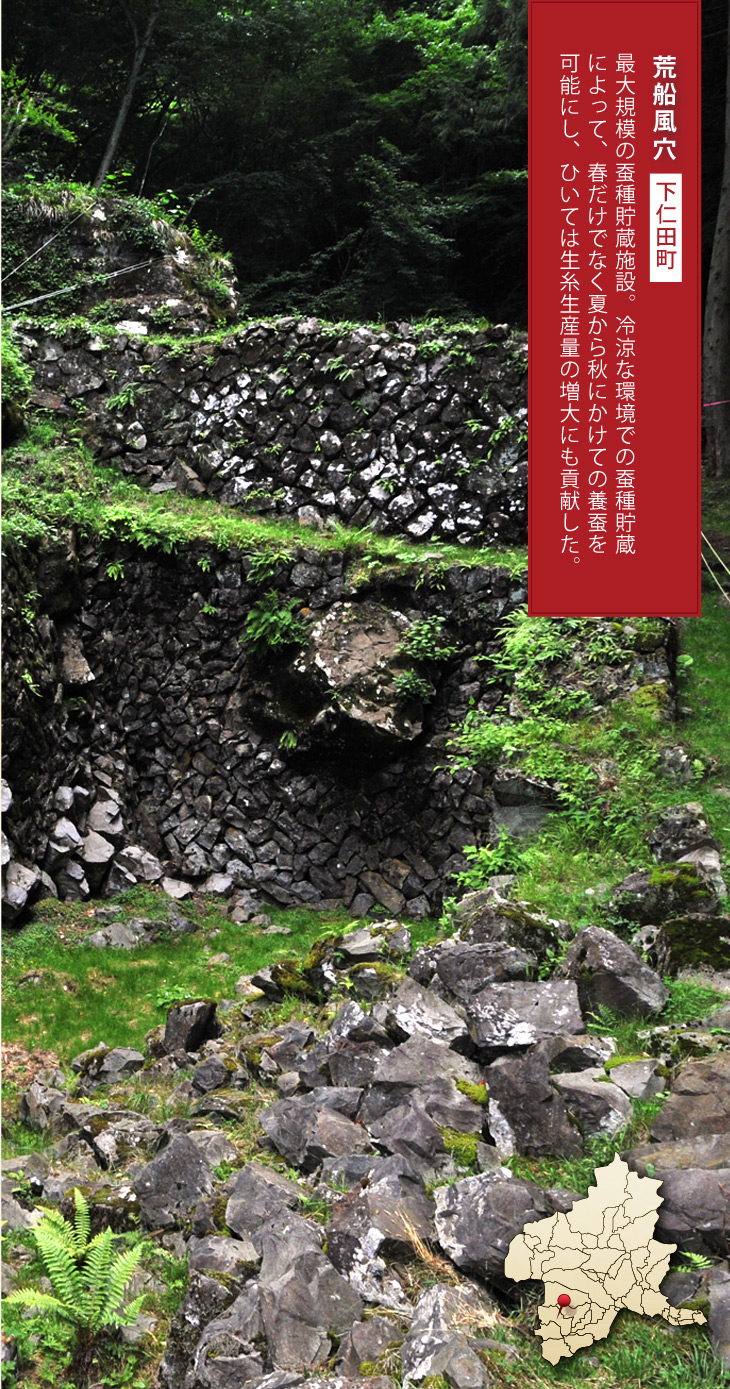3年かけ納得の染め 紅板締めを復元 「たかさき紅の会」/幻の技法試作13回 絹の文化復活に期待
- 掲載日
- 2007/10/17

古い型板の傷み具合を調べる市川さん(右から2人目)ら
かつての染め織物の産地、高崎市を拠点に活動し、三年がかりで幻の染色技法「紅板締め」の復元に成功した「たかさき紅の会」(吉村晴子代表)が九月から、紅板締めの普及に向けて動きだした。残された古い型板を補修し、新たに天然染料による染めにも挑戦する。手業として極めながら、来年度には紅板締めを体験できるワークショップを開き、赤と白が織りなす世界の魅力を広げていきたい考えだ。(高崎支社報道部 天笠美由紀)
高崎市相生町で吉村代表(72)が主宰する「染工房はるる」。九月十五日、中心メンバー七人が赤い染料の染み付いた紅板締めの型板七十四枚を並べ、板の割れや反り具合を調べた。

重に、型板に生地を挟むメンバー
型板は吉村代表の祖先が一八四五年、同町で創業した吉村染工場(~一九三二年)に残されていたもの。中には真っ二つに割れ、端を糸や針金で留めた板もある。傷んだ板は太田市新井町の元大工、市川栄沙さん(79)が持ち帰り、修復作業を始めている。
薄絹の染色技法の一つ、紅板締めは模様を彫った型板に生地を挟んで染料液をかけ、緋色(ひいろ)地に白い模様を染め抜く。江戸から昭和初期にかけて礼装用着物の合着などに使われ、女性が隠れたおしゃれとしてまとった。
◇全国で職人不在
紅染め専門の染物屋だった同工場は四代目吉村平七が、江戸期まで京都で独占的に使われていた紅板締めを採用。やがて需要の落ち込みや多色技術の普及によって生産が途絶え、全国で染められる職人はいないという。
「なぜ、赤と白でこんなにきれいに染められるんだろう。裏地にこんないい表現をするのかと魅力を感じた」と同会メンバーの余川淑子さん(68)=高崎市飯塚町。加藤昭子さん(74)=同市赤坂町=も「紅(もみ)絹の赤は見るだけで元気が出る」とすっかり引き込まれた様子だ。
同会は一九九五年、染色や和装を通じて集まった人たちで結成。三年前、県の「文化の芽」支援事業として紅板締めの復元に乗り出した。
繊維や美術史の専門家も加わり、復元前には同工場に残された資料などを基に当時の産業構造や生活習慣を調査。彫りかけの型板を参考に新しい型板を復元し、板締めに使う枠も製作した。
◇手探りの作業

上がった作品を広げ、出来具合をチェック。染め残しやむらがないか確認する
昨年十月、実際に染色作業を始めたものの、試行錯誤の繰り返し。資料に工程は書かれていても、具体的な記述はなく、生地の畳み方から型板を締める強さ、染料液の濃度とかけ方を検証しながらの作業が続いた。
染色を約十年手掛けてきた長谷川葉子さん(62)=同市上中居町=は「今までやってきたことが通用しない。一度、途絶えたものを復元させる大変さを実感した」。四カ月掛けて型板を復元した市川さんも、「使ったホオノキは硬い木で、肩が痛くなるほど力が必要だった。先人の彫る技術に驚いた」と振り返る。
◇薄い生地で成功

島屋で披露された紅板締めを使った着物。鮮やかな色彩が訪れた人たちを魅了した
十三回にわたる試作を重ねた結果、従来より薄い絹を使うことで今年三月、復元に成功。五月には、染め上げた裏絹を使って仕立てた着物を高崎高島屋で一般公開した。
活動を後押しする県繊維工業試験場の主任研究員、新井正直さん(51)は「かつては薄い絹を重ねて着ていたが、高度成長期から着る物が厚くなった。薄絹は薄いからこそ軽くて柔らかくて、膨らみを持ち温かい。忘れられている絹の文化を復活できれば」と、生地の研究の必要性を説く。
◇次はベニバナで
これまで化学染料を使ってきたが、十一月には明治以前に行われていたベニバナによる紅板締めに挑戦する。復元に使ってきた古い型板の補修とともに、新しい型板も補充しながら来年度のワークショップに向けて準備を進めている。吉村代表は「今後は職人としての技を確立させ、多くの人に体験してもらいながら紅板締めの魅力を知ってほしい」と話している。