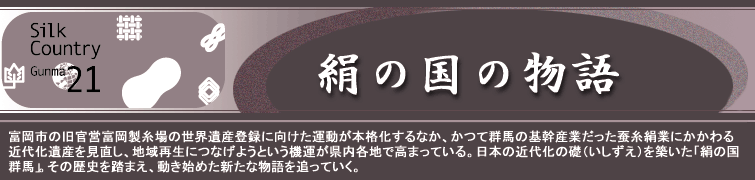第2部・織都桐生の近代化遺産
3・織物版の地産地消 県産生糸を桐生の技で 2005/10/27

のこぎり屋根工場で、ぐんま200を使って帯地を織る江雅織物
ガシャン、ガシャン。のこぎり屋根工場の仕事場に、昔ながらの機音が響く。桐生市三吉町の江雅(えまさ)織物は碓氷製糸農業協同組合(松井田町)の生産する生糸「ぐんま200」で帯地を織る。この糸を使い始めたのは古い話ではない。高村育也組合長(59)は「桐生や大間々の機屋は5年ほど前からぐんま200を使い始めた。輸入糸の方が安いのに。桐生がなければ碓氷製糸は立ちゆかない」と感謝する。
織物は養蚕・製糸・染色など複雑で分業の進んだ工程を経て生まれる。一つの工程がなくなればシステムが崩壊しかねない。「群馬の絹」活性化研究会の会長でもある江雅織物の江原毅社長(70)は「最初は立場から、今は素性の分かる糸として使っている」と導入のきっかけを語る。
◎細心の注意
機屋の第一線で大切な糸を扱う女性たちは、手肌が荒れないように細心の注意を払う。「ささくれ立っている手で生糸に触れると、けば立つ。良い織物のために、特に冬場は手をまめに洗い、軽石で指先を手入れし、自分にあったハンドクリームを医者で手に入れる人もいる。機屋で働く女性が受け継いできた当たり前の姿勢です」。織機に45年向き合ってきた桜井フミエさん(60)は織物のまちの心意気を、こう表現する。
桐生や大間々でぐんま200を使う賛同者は増えている。着物を購入しても一枚か2枚の時代。「高くとも良いものを」と、織物版の地産地消が始まった。全国でも2ヶ所しかない製糸会社と織物の大産地の新しい付き合いは、互いに「氏素性の知れた糸を、地元の優れた技術で丁寧に織る」の意識が支えている。
◎連携目指す
内産生糸を使った絹製品の生き残りを目指す動きは、ほかにもある。碓氷製糸も加わって、県内の織物卸売会社、織物職人、機屋などの連携を目指した「日本蚕糸絹業開発協同組合」が今年3月に生まれた。桐生市の機屋として参加している佐啓産業の社長で、同組合理事の佐藤好雄さん(49)は「群馬の絹を残したい気持ちは強い。差別化された商品を作れれば、十分生き残る道が生まれる」と展望する。
29日に桐生で行われる「近代化遺産の日」制定記念事業のパネルディスカッション「絹の道をささえた近代化遺産」には、パネリストとして碓氷製糸の前組合長、茂木雅雄さん(75)が参加する。茂木さんは「国産品にこだわる新しい動きを、会場に足を運んでくれる人たちに、ぜひ紹介したい」と話している。