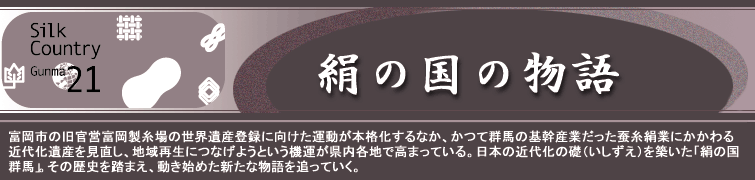第4部・片倉工業の足跡
9・輸入量増え糸価低落 工場閉鎖 2006/1/11

富岡工場閉鎖の日。退職する人、熊谷工場に転勤する人、それぞれが別れを惜しんだ=1987年3月
1987(昭和62)年1月、片倉工業富岡工場の従業員96人に同年2月末での操業停止が伝えられた。
外国からの生糸輸入で、人件費が上がった国内の蚕糸業は太刀打ちできなくなっていた。富岡工場では六年前から、毎年約1億4000万円の赤字続き。年間6000俵(1俵60キロ)の生産力がありながら、’86年の生産量は約3200俵にとどまった。
同工場の工務課長だった直井幸夫さん(75)=下仁田町馬山=は「富岡工場は歴史があるので、(片倉の中でも)最後まで残るのかなという感じはあったのだが…」と語る。しかし、経営環境は厳しく、「閉鎖はやむを得ないと思った」と振り返る。
当時、片倉は富岡工場のほか、埼玉の熊谷、岩手の千厩、鹿児島・末吉の3工場が製糸の灯を守っていた。「富岡と熊谷。どちらが最後まで残るのか」。従業員の認識も厳しいものだった。
◎期中改定
同工場の労組支部長、梅沢幸男さん(75)=富岡市下高瀬=は他の従業員よりも一足早く、操業停止を知った。「組合として、従業員の転勤先や、定時制高校に通う女性たちの就学問題などを会社と交渉した。後は経済的な条件闘争だった」。梅沢さんは職場ごとに集会を開き、従業員の動揺を抑えた。
富岡工場はなぜ閉鎖したのか―。生糸の価格を見ると、閉鎖理由の一端が浮かび上がる。
60年代の初め、生糸は国内の生活水準が上がったことで需要が増え、相場が高騰した。そのため’65年から中国や韓国から生糸を輸入するようになったが、輸入量が年々拡大する一方で、国内は景気後退で需要が伸び悩み、糸価は低落した。
政府は糸価安定のため、民間と共同出資で日本蚕糸事業団を設立。審議会が年度末に答申する基準糸価に基づき、生糸の買い入れ・市場放出を行い、価格を調整した。
繭価格は糸価の約8割を目安に価格が決まる。養蚕所得の増加を求める農家は政治力を背景に糸価の引き上げを要求。基準糸価は制度創設の’66年度から、’85年度まで上昇した。碓氷製糸農業協同組合前組合長の茂木雅雄さん(75)=松井田町五料=は「基準糸価が年々上がるのだから、製糸業は翌年糸にするための繭を買って持ってさえいれば、もうかる仕組みだった」と明かす。
だが、同事業団はやがて買い入れ一辺倒になり、17万俵を超える在庫はそれ自体が市場への圧力になった。制度は破たん寸前で、政府は’84年11月、生糸1キロ当たりの基準糸価を2000円下げる「期中改定」に初めて踏み切った。
◎最後通告
準糸価は以降、下落基調に転じた。富岡工場の閉鎖が発表される直前、2度目の期中改定が行われ、基準糸価はさらに2200円引き下げられた。それは製糸業に対する最後通告に等しかった。
柳沢晴夫社長(故人)は、製糸業の象徴ともいえる富岡工場の閉鎖を決断した。社員の一部は決定を「政府への抗議」と受け止めたという。
同社は8年後、最後に残った熊谷工場を閉め、製糸業の歴史に幕を引いた。製糸業からの撤退について、柳沢社長は後日、こう語ったという。
「創業以来の片倉の製糸を切った自分の責任はいつも感じている。富岡工場は日本の近代化を進めた大切なところだ。会社が厳しくてもずっと守っていく」