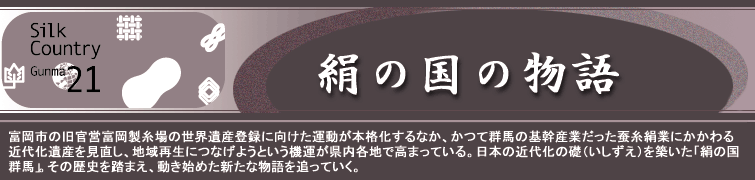第3部・碓氷製糸の挑戦
7・座繰り 修業重ね売り物に 2005/12/16

単身群馬に飛び込んで丸4年になる東さん。上州座繰りの後継者として、本県に欠かせない存在となった
日当たりの良い一戸建てのアパート。窓ガラス越しの朝日を浴びて、ひきたての座繰り糸がつややかに輝く。上州座繰り器を回す東(ひがし)宣江さん(29)=前橋市古市町=の表情も、自然と和らいだ。
4年前の冬、寒い空っ風が吹いていた。京都の呉服屋などでデザイン業務をしていた東さんは、絹に関心をもったことがきっかけで、上州座繰りを知り、「発祥の地だから、きっと学ぶ場があるはず」と、初めて群馬を訪れた。
富士見村で糸ひきを生業とするおばあちゃんを訪ねた。県が開いた座繰りの講習会にも参加した。「その先」を探して、方々に声を掛けた。
◎将来の柱
「若いのに熱心だな。これは面白い」。当時、碓氷製糸農業協同組合(松井田町新堀)の組合長だった茂木雅雄さん(75)は、実績も技術もない東さんを受け入れた。採算が合わないことは覚悟の上。「趣味で座繰り糸の織物を作る人たちがいる。将来は座繰り糸が経営の一つの柱になるかもしれない」。生糸需要の新たな可能性が生まれることを願っていた。
東京でグラフィックデザインの仕事をしていた中野紘子さん(28)=新町=は、都会の生活に合わず帰郷していた。「群馬ならではの仕事をしたい」。そう考えていた時に、東さんの存在を知り、自分も一緒に碓氷製糸で働くことを願い出た。
朝8時から夕方5時までは、器械製糸の仕事。その後、寮の自室に帰ると、パンパンに張った足を休める間もなく、座繰り器を回した。小枠にひき上げた生糸は、その日のうちに枠から外す揚げ返しが必要。夜更けに真っ暗な工場へ戻り、糸の仕上げ作業をした。寝る間も惜しんで、修業を続けた。
◎心が和む音
先が見えない不安があった。それでも、絹を仕事にできる充実感があった」。中野さんは当時の心境を語る。
四カ月余りが過ぎ、二人の糸の品質は向上していた。「これならば売り物になる」。上司の判断で、昼間の勤務時に職業として座繰り器を回すことが認められた。二人はプロの座繰り糸のひき手になった。
碓氷製糸工場内の一室。2台の上州座繰り器が、並んで設置された。歯車が奏でる「カラ、カラ、カラ」という小気味よい音は、不思議に職員たちの心を和ませた。けれどもそれは、2人にとって、生産効率とのせめぎ合いの始まりでもあった。