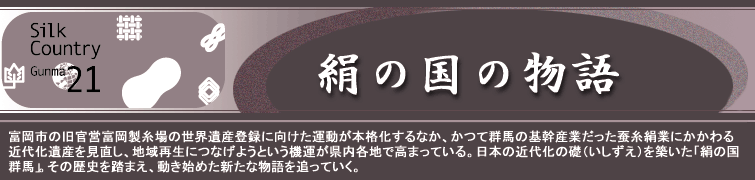第4部・片倉工業の足跡
2・開明社 明治の輸出ブランド 2006/1/3
2003年5月、長野県岡谷市の鶴峯公園で、「製糸王」と呼ばれた初代片倉兼太郎(1849―1917年)の銅像が60年ぶりに復元された。銅像は戦時中の金属回収令で供出され、台座だけが公園に残されていた。
銅像は地元有志らが、諏訪地方の輝かしい歴史と先人の遺業を語り継ぎたいと寄付を募って復元した。除幕式には片倉家五代目当主の片倉康行さん(71)が出席した。台座を含め高さ約九メートルの銅像が復元されたことについて康行さんは「銅像は過去の遺物かもしれないが、見上げたときは感激した。これも初代兼太郎の人徳だ」と喜ぶ。
片倉工業の起源は、片倉市助が1873(明治6)年、長野県旧川岸村(現・岡谷市)で十人繰りの座繰り製糸を始めたことにさかのぼる。
片倉家は江戸時代に帰農して代々農業を家業とした。市助には四人の息子がおり、長男から順に兼太郎、光治、五介、佐一といった。片倉はこの4兄弟が活躍、後に世界最大の製糸会社に発展させていく。
’76年、家督を継いだ兼太郎は農業をやめて、製糸業に乗り出す決意を固めた。片倉製糸紡績20年誌によると、兼太郎は「地主は貧窮農民を相手に一家の経営を図り、地主として立つことは自己の性格に合わず。むしろ先祖伝来の農を中止しても、時勢に順応し、国富増進に資する事業に進むにしかず」とこの時の気持ちを語っている。
兼太郎は’78年、天竜川河畔に32人繰りの洋式器械製糸「垣外(かいと)製糸場」を建設した。同製糸場は長さ13間(23.6メートル)、奥行き七間(12.7メートル)で、天竜川にかけた直径3丈7尺9寸(11.5メートル)の水車を動力に利用した。
当時、生糸は「梱(こうり)」という単位で取引された。一梱は約34キロ。同製糸場では年間17梱を生産できたが、まだ出荷量に問題があった。兼太郎は同業者八人と輸出用生糸を共同出荷する「深沢社(みさわしゃ)」を設立。翌年には近隣からさらに多くの業者を集め、「開明社」を組織した。
開明社で兼太郎は同業者をまとめあげ、全国初の本格的な生糸の品質管理に乗り出した。
生糸商からの要望は(1)二本揚がりという糸の混乱をなくす(2)糸が切れたら必ず結ぶ(3)糸の太さを均一にする―という規格の統一だった。だが、当時の製糸業者はまだ10釜前後の小規模経営が中心で、要望に応えるのは難しかった。
開明社は問題を解決するため、共同揚げ返し場を新設。小枠で持ち込まれた生糸を共同で揚げ返すことで品質と荷口の統一を図った。これにより開明社の名声は日増しに高まり、後に「信州上一番格(しんしゅうじょういちばんかく)」と呼ばれる輸出用の代表的な生糸を製造する基盤となった。
片倉発展の要因について、東京大学名誉教授の石井寛治さん(67)は「当時のアメリカは力織機に合う生糸を求めていた。開明社の糸は品質がトップということではないが、精密なアメリカのマーケットに合う製品を作った」と開明社の功績を指摘する。
横浜では開明社製生糸がブランド価値を持つようになり、開明社というだけで高値で取引されたという。名声は片倉の資金調達を容易にした。片倉が拡張路線を突き進む際、生糸問屋や銀行が積極的に融資するようになり、片倉の成長を後押しすることになった。