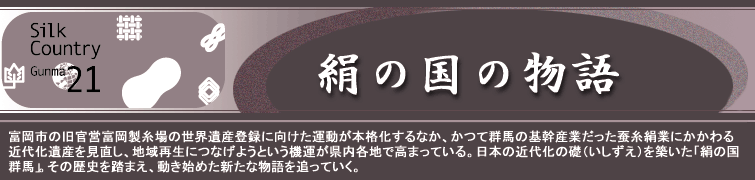第3部・碓氷製糸の挑戦
1・蚕糸業復興勝負の時 純国産に未来託す 白生地 2005/12/6

職員が慌ただしく作業する碓氷製糸の工場内部。県内唯一、全国でも2つしかない器械製糸場として、製糸業の灯を守っている
輝くばかりの白さに驚きの声が上がった。今年九月、県庁で開かれたぐんまシルク認定委員会。「本県産」の認定を受けるため公開された一点の白生地に、委員らは思わず目を見張った。
「日本を代表する生地になるかもしれない」。認定委員で江戸小紋染色作家の藍田正雄さん(65)=群馬町足門=は、そう直感したという。ラベルには真っ赤な日の丸と、「純日本の絹」の文字が誇らしく記されていた。
◎「新小石丸」
白生地を作ったのは、高崎市問屋町の日本蚕糸絹業開発協同組合。今年4月に設立したばかりの新しい組織だ。
発起人の小林幸夫さん(46)=高崎市並榎町=が「群馬の絹産業は存亡の危機にある。関係者が一丸となって付加価値の高い絹製品を作らなくては、明日はない」と、経営する絹問屋の取引先などを通じて呼び掛けた。この訴えに、同じ志をもつ製糸、機屋、染色、卸売りなど、国内絹産業の“川上から川下”までの業者が結集。複雑に分業化された絹業界が縦につながる前例のない組織が誕生した。
その組合が「蚕糸復興のために、正真正銘の国産ブランドを」と製作したのが、群馬オリジナル蚕品種「新小石丸」を使った白生地だった。
本県の蚕糸業は、花形産業として日本の近代化、戦後の農村の繁栄を支えてきた。しかし、近年は外国産の安い生糸に押され、国産生糸の価格は低迷している。
今年の県内養蚕農家は647戸、収繭量は285トン前後。どちらも過去最少だった昨年をさらに下回った。小林さんの言う「存亡の危機」が現実味を増している。
松井田町役場から西へ1キロ、碓氷川のほとり。妙義山を背に、古い工場が建っている。46年前、地元養蚕農家により設立された碓氷製糸農業協同組合だ。煙突から立ち上る煙は、最盛期の3分の1に減った。それでも、製糸の灯を守ろうと、ひたむきな操業を続けている。
事務室の中央。決算書類に目を通す高村育也組合長(59)が現状を語る。「どん底だよ、この業界は。今のままじゃ、おしまいだ」
しかし、言葉とは裏腹に、険しいまなざしからは、このままでは決して終わらせまいという強い使命感が伝わってくる。
◎希少性前面
価な外国産に市場を奪われるなか、碓氷製糸が本年度から本腰を入れているのは、国内産生糸の質の高さと希少性を前面に打ち出してアピールする戦略だ。
日本蚕糸絹業開発協同組合の群馬オリジナル蚕品種「新小石丸」の白生地づくりも狙いは同じで、高村さんも発足メンバーの一人として副理事長を務めている。
「外国産と差別化した、付加価値のある糸が作れるなら、復興も夢じゃない。この先2年間が最後の勝負になると思っている」
◇碓氷製糸農業共同組合
唯一操業している器械製糸場。松井田町や同町内の3農協などが出資し合う協同組合形式で、1959年12月に設立。その後、3000人近い地元養蚕農家が出資に加わった。現在の組合員は985人。今年は非組合員も含め、全国約1300戸の養蚕農家から繭が出荷された。従業員は38人。年間の生糸生産量は54トンで、国内総生産量の7割以上を占めている。
◇碓氷製糸農業協同組合
国内蚕糸業に冬の時代が訪れている。外国産生糸に押され、国内の器械製糸場はわずか二社となった。その一つ、碓氷製糸の経営環境は極めて厳しい。そんな中でも、養蚕農家を守るため必死に踏ん張り、活路を見いだそうとしている。第三部では、国内蚕糸業の復興を目指す碓氷製糸の挑戦と、それを支援する人々を追う。