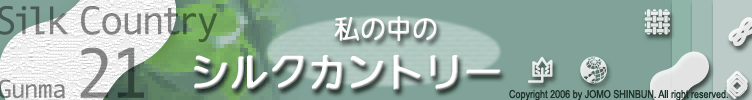織機復元 欠けた部品は手作り 石橋 政雄さん(76) 板倉町飯野 掲載日:2008/01/29

復元した織機(手前)への思いを語る石橋さん
板倉町歴史資料館の2階に眠ったままになっていた機織り機3台を復元した。いずれも町内の旧家にあったもので、解体され資料館に保存されていた。元の姿に戻そうにも、どれもバラバラの状態で組み立て方すらわからない状況になっていたものばかり。手がつけられずに困っていた町から2000年に依頼された。
「頼まれたら期待に応えたくなる性分だから、徹夜で作業した。復元できたのは織機を子供のころに見たことがあったから。でも、もともと同じ人間が組み立てたもの。やってできないことはないよ」
キュウリ栽培などの農業が盛んな板倉町は、その影響からか、県内で最も早く養蚕離れが進んだ地域の1つ。かつては実家も養蚕をやっていたが、1945年にいち早くキュウリ農家に転換した。
解体されていた機織り機には、保管されているうちに紛失した部品があった一方、まったく違う道具の部品も混ざっているなど、復元作業は困難を極めた。老朽化してそのままでは使えないため、自ら木を加工して新たに作り上げた部品も多い。
「養蚕は小学生のころまでしかやっていないから、あまり記憶がない。でも、機織りは農閑期に母や祖母もやっていたのをよく見ていたから覚えていた。必要なものは自分で作る習慣があったので、話をもらったときに何とかなるような気がした」
苦心の末に組み立てられた織機は、それを見本に町職員らがさらに2台を復元し、現在5台になっている。
町に伝わってきた織物文化を若い世代に継承するサークル「織り姫」の活動に使用され、受講生の主婦らが「ぱったんぱったん」と小気味いい音を奏でている。
「復元してはみたけれど正直なところ、まさか本当に織れるようになるとは思わなかった。実際に使えるようになるまでには相当な苦労があったと思う。自分の組み立てた織機が町の伝統継承に役立ってくれればうれしい」